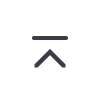ごあいさつ
- 当院について
理事長挨拶

医療法人 城南ヘルスケアグループ
理事長
馬場 秀夫
ばば ひでお
この度、小野友道先生の後任として、くまもと南部広域病院の理事長を拝命しました馬場秀夫です。簡単に自己紹介しますと、2005年より2024年まで熊本大学消化器外科の教授をしておりました。退官の3年前からは大学病院の病院長、副学長も兼務しておりしました。医師としての専門領域は消化器疾患、特に消化器癌の外科治療や化学療法です。大学を退官した後、現在は一般財団法人化学及血清療法研究所の理事長を兼務しております。
当院は12の診療科を有し、神経難病外来・もの忘れ外来といった専門外来や健診、訪問診療などを通じて、患者さまお一人おひとりの人格や権利を尊重し、高度な医療安全管理の下、常に質の高い医療を提供することで地域住民の皆様の健康増進に最大限寄与できるように、日々取り組んでおります。また、他の医療機関との連携を強化することで地域全体の医療福祉の向上に貢献できるように取り組んでおります。
少子高齢化が進む中、今後の医療に求められる内容も変化していくことが予想されますが、地域の医療ニーズを的確に把握しながら、病院機能を進化させていく所存です。今後とも皆様のご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いします。
院長挨拶

医療法人 城南ヘルスケアグループ
くまもと南部広域病院
院長
町田 二郎
まちだ じろう
日中と夜の寒暖差の影響か、今年は桜の咲く期間が長く、世の中は新年度春のすがすがしさを心行くまで味わうことができる喜びに満ち溢れているようです。
4月1日にくまもと南部広域病院にも新たに3名の医師、3名の看護師、10名のセラピスト、1名のソーシャルワーカー、1名の栄養士、1名の事務職員を迎え若返ることとなりました。新しい風が吹いてくることでしょう。当院の理念は「働く職員の幸福を追求し、医療、介護、予防事業を通じ、住み続けることのできる地域社会作りに貢献します」です。つまり「職員を大切にすること」と「業務による地域貢献」の二本立てになっています。後者が経営に直結することから、いきおい、事業計画の推進に心がいきがちですが、歓迎式で新入職員を前にした時、前者の「職員を大切にする」理念が大きく再認識されました。
言うまでもなく国の外も内も、様々な問題でたいへんに混とんとしています。人と人の関係構築が難しい時代ともいわれますが、いつの時代にも同じことが言われていたのかもしれません。人の言葉に耳を傾け、人の思いを理解し、自分の思いも上手に相手に伝える、意思疎通の大切さが昔から言われてきましたが、相手を前にした時の遠慮、思い込み、恐れ、面倒くさい、などの入り混じった複雑な感情から、意思疎通をうまく果たせないことは少なくありません。結局は自分自身の心のハードル、心の未熟さが原因なのです。SNSは相手を前にした時に沸き起こる複雑な感情を感じないために、簡単に自分の意見を発信できますが、様々な負の側面が波紋を呼んでいます。
「働く職員の幸福を追求する」理念は、日々唱和をすれば浸透するものではありません。理念の主語は「法人」とはいうものの責任主体は経営陣なのです。このことを改めて痛感し、理念達成のために小さなことの実践を積み重ねていく決意を新たにしたところです。さくら散る後に葉緑素をたっぷりと蓄えた青々と茂る緑が広がることを楽しみにしています。
-
院長挨拶(2024年)
温故知新
当院は70年近い歴史があり、時代の変化に応じて少しずつ変革を遂げてきました。その時々の先達は大変な思いをしながら歴史を紡いできたに違いありません。近年の変化はその中でも大きな変化を迎えている時期の一つではないかと感じています。日本の急速な少子高齢社会への突入速度は世界的に見てもまれと言われています。IT、AIによる第4次産業革命が始まり、情報や物や人の移動速度が増し、人々の価値観がますます多様化しています。気候変動の増加による災害が増加し、国際関係は新たな局面を迎えています。先の見えない時代と言われる所以です。
しかし変化を好機ととらえればどこまで発展していくのか楽しみだ、という見方もできそうです。少子高齢社会を乗り越えるため、仕事や生活にかかわる様々な手続きの無駄をITにより能率化する試みが始まっており、仕事や行政サービスの質が向上するでしょう。IT化によるライドシェアが進めば、移動手段のないお年寄りでも今以上に移動が便利になるでしょう。働き方改革が進みオンライン就業が整備されれば、離れたところに住んでいても、決まった時間に出社しなくても、自分の持てる能力を生かす働き方ができるでしょう。
一方、病院のように職場に来なければ始まらない仕事もありますし、人が対面で顔を合わせて働くことで生まれるエネルギーや喜びもあります。何より人間の肉体構造と喜怒哀楽の感情は、現生人類20万年の歴史で大きく変わっていません。そうであれば人が集まる職場は働きやすく、やりがいを感じられる職場でなければなりませんし、職員も一社会人としての倫理観と責任意識を持った行動をしなければなりません。そうでなければ当院をご利用なさる方々に質の高い医療や介護を提供することもできません。人間の長い歴史で培われた、人としてあるべき考え方を大切にしなければなりません。
私たちは故(ふる)きを温(たず)ね新しきを知り、変化を恐れることなく医療、介護、福祉の領域で地域の皆さんの生活を支える機能を備え、安心して働ける職場をつくり、社会に貢献していく所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。