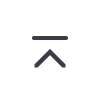医療チーム
- 医療関係者の方へ
感染防止対策室(ICT)
病院内には、感染症の治療をしている人や、細菌・ウイルスなどを体内に保有している人が多くいます。体力が弱った人がひとたび感染症にかかると、命に関わったり、治療に余分な費用や期間が掛かることがあります。肺結核やインフルエンザ、ノロウイルス感染症、抗生剤が効かない多剤耐性菌などは、特に大きな影響を与えます。
病院職員が感染の媒介者になることがあるため、全職員がマニュアルに沿った感染症の発生防止の対策を徹底。院内で発生した全ての情報を各科で共有し、蔓延を防ぐ取り組みを実践しています。
構成メンバー
院長、医師、看護師長、看護師、薬剤師、臨床検査技師
- 各部署長が協議する院内感染対策委員会
- 各部署の感染対策担当者
- 院内感染対策を専門とし、実際に立案・行動する感染制御チーム
感染制御チームの役割・業務内容
- 病院内で起こる感染症の監視のため、院内感染対策部会と協力しながら、各部署の環境整備や感染症の発生状況・抗生剤の使い方を調査する
- 感染症が発生した場合、迅速に報告を受け、院内感染対策委員会、保健所などと相談しながら蔓延を防ぐ
- 感染症に関する職員の知識向上のため研修会を開催する(全職員対象:年2回)
- 院内感染対策の手本となるマニュアルを作成(マニュアルは定期的に見直し改訂する)
- 地域全体での感染対策を促進するため、連携病院で行われる会議では院内感染に関するデータを提出し調査に協力する他、連携カンファレンスに参加し知識習得を図る
褥瘡対策チーム
褥瘡とは、寝たきりなどによって体重で圧迫されている場所の血流が滞ることで生じる皮膚病変のことを言います。一般的に「床ずれ」とも言われており、圧迫を受けやすいお尻や踵(かかと)などの部位の、褥瘡が出来やすい箇所(骨が出っ張っている部分)に皮膚の赤みやただれ、潰瘍(かいよう)などを生じます。
褥瘡対策チームは、褥瘡が発生しやすい患者さまの褥瘡を予防し、既に褥瘡を有している場合は早期治療を目指し、治療方法の提案や療養環境を整えるための活動を行っています。
構成メンバー
医師、皮膚・排泄ケア認定看護師、看護師、リハビリスタッフ、管理栄養士、薬剤師
褥瘡対策チームの役割・業務内容
- 入院患者さまの危険因子、日常生活自立度を評価し適切なマットレスの選択を実施
- 褥瘡に関する院内教育
- 褥瘡保有患者の褥瘡状態評価、回診
- 褥瘡対策マニュアルの改訂
- 褥瘡予防環境整備、体圧分散寝具管理
- 褥瘡対策委員会(月1回)
院内の褥瘡発生件数、褥瘡有病率及び発生率の調査・分析・評価
栄養サポートチーム(NST)
患者さまに最適な栄養療法を提供することを目的とした、多職種により構成されたチームとなります。
NSTでは、病気や嚥下機能低下などにより食事摂取が十分ではない患者さまや栄養状態の改善が必要な患者さまに対して、各分野の専門職が知識や技術を持ち寄り、適切な栄養補給方法の提案や疾患の回復、合併症の予防に有用な栄養管理方法の提案などを行っています。また内科と精神科を併せ持つ当院では、精神科病棟でもNST回診を行っています。
適切な栄養管理により栄養状態を改善させることが、治療効果を高めて予後を改善することや合併症を予防することにつながります。
構成メンバー
医師、管理栄養士、看護師、皮膚・排泄ケア認定看護師、薬剤師、臨床検査技師、リハビリスタッフ(PT・OT・ST)
栄養サポートチームの役割・業務
内容
- NST回診対象患者の抽出
患者さまの栄養状態の評価(スクリーニング)を行い、NST対象者を抽出します。 - NSTラウンド・NST回診・カンファレンス
毎週月曜日にNSTメンバーで病棟ラウンド(回診)を行います。NST対象となった患者さまの対応策を協議し、その結果をNST回診記録にまとめ、提言します。 - NST委員会の開催
第2週火曜日に委員会を開催し、毎月の症例報告や栄養状態報告、栄養ケアに関する情報提供などを行っています。
医療安全チーム
医療法施行規則に基づき医療安全管理委員会と医療安全管理部を設置。2016年にマニュアルを改定し、ヒヤリハット事例や医療事故の事例が発生した場合の報告体制を「見える化」しました。
チームの活動にあたっては、各部署の医療安全管理メンバーと連携し、各部署で発生しているヒヤリハット等についての情報収集、データ集計を行い、必要に応じて委員会で対策を講じていきます。委員会で決定した対策は、医療安全管理メンバーを通じ、各部署の職員にフィードバック。安全に向けた全院的な行動につながるよう働きかけを行っています。
構成メンバー
院長、医師、事務部長、看護部長、看護師長、薬剤科長、栄養科長、リハビリ科長
医療安全チームの役割・業務内容
- ヒヤリハット事例を全部署から集め、原因や対策について話し合いを行う
- 事故等に関する診療録や看護記録等への記載が、正確かつ十分に行われているか確認を行う
- 場合によっては適切な指導を行う
- 患者さまやご家族へ、事故発生の対応状況等についての説明を行う
- 事故の原因究明が適切に行われているか確認し、必要な指導を行う
- 医療安全に係る職員の教育、研修を行う
- 医療安全管理マニュアルの見直しや改訂
認知症ケアチーム
少子高齢社会となった日本では、認知症を発症する方の数は今後ますます増加していくことが予想されます。認知症の方が入院する場合、環境変化への適応に時間がかかり、認知症の症状の悪化や入院期間の長期化が懸念されます。
認知症ケアチームは、認知症による行動心理症状や意思疎通の困難さにより身体疾患の治療が円滑に進まないことが見込まれる患者さまの意思を汲み取り、認知症の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられるようにすることを目的として活動する専門チームです。認知症治療・ケアに関する専門知識を持った多職種のスタッフがチームとなって主治医や担当看護師と協力し、入院生活のサポートを行います。
構成メンバー
脳神経内科医師、精神科医、認知症認定看護師、精神保健福祉士、認知症ケアに係る適切な研修を受講した看護師、セラピスト
認知症ケアチームの役割・業務
内容
- 定期的な病棟回診とカンファレンス
- 認知症の行動心理症状に対する環境調整、ケアの提案
- 適切な薬剤調整の提案
- 身体拘束の予防・早期解除へ向けた取り組みの助言
- 認知症ケアに関する研修会の開催